著者:中島敦 1976年3月に筑摩書房から出版
狐憑の主要登場人物
シャク(しゃく)
ネウリ部落の若者。 弟の死をきっかけに、憑きものに憑かれるようになる。
デック(でっく)
シャクの弟。北方部族の襲撃により死亡する。
長老(ちょうろう)
最も有力な豹の爪を持つ家柄の長老。
狐憑 の簡単なあらすじ
ネウリ部落のシャクは、湖上で生活を営む未開の部族の、最も平凡な一人でした。
しかしある日、北方から剽悍な遊牧民ウグリ族がやってきて、集落を襲いました。
そして、その時に、弟のデックが死んでしまったのです。
それからしばらくして、シャクは妙なうわ言をいうようになりました。
周囲の者は、シャクに憑きものがした噂しました。
しかし、憑きものの形を借りてシャクが語る話は、あまりに面白く聴衆を惹きつけました。
そして、あれはシャクが想像したことをしゃべっているのではないか?と疑問を持つものが現れました。
狐憑 の起承転結
【起】狐憑 のあらすじ①
ネウリ部落のシャクに憑きものがしたという評判でした。
色々なものがこの男にのり移るのだそうです。
鷹だの狼だの獺だのの霊が、哀れなシャクにのり移つて、不思議な言葉を吐かせるということです。
後にギリシア人がスキタイ人と呼んだ未開の人種の中でも、この種族は特に一風変わっていました。
彼等は、野獣の襲撃を避けるために湖上に家を建てて住んでいました。
幾千本かの丸太を湖の淺い部分に打ち込んで、その上に板を渡し、そこに彼等の家々は建っていました。
麻布の製法を知っていて、獣皮と共にこれを身にまとい、馬肉、羊肉、木苺、菱の実を食べ、馬乳や馬乳酒を飲みました。
ネウリ部落のシャクは、そうした湖上民の最も平凡な一人でした。
シャクが変になり始めたのは、去年の春、弟のデックが死んで以来のことでした。
その時は、北方から剽悍な遊牧民ウグリ族の一隊が、馬上に偃月刀を振りかざして疾風の如く部落を襲ってきました。
湖上の民は必死になつて防ぎました。
初めは湖畔に出て侵略者を迎え撃った彼等も、名だたる北方草原の騎馬兵にたまりかねて、湖上に退きました。
舟を操るのが巧みでない遊牧民は断念し、疾風の樣に北方に帰っていきました。
あとには、頭と右手の無い死体だけが残されていました。
頭と右手だけは、侵略者が切り取って持って行ったのです。
シャクの弟のデックの死体も、そのような辱しめを受けて打ち捨てられていました。
弟の死体を前に、シャクは暫くボーっとしたまま慘めな姿を眺めていました。
その樣子が、どうも、弟の死を悼んでいるのとは違うように見えた、と、後あとで言っていた者がいました。
【承】狐憑 のあらすじ②
その後間もなくシャクは妙なうわ言をいうようになりました。
何がこの男に乗り移って奇怪な言葉を吐かせるのか、初めは人々には判りませんでした。
言葉つきから判断すれば、それは生きながら皮を剥がれた野獣の霊ででもあるように思えました。
一同が考えた末に、それは、彼の弟デックの、切り取られた右手がしゃべっているのに違いないという結論に達しました。
四五日すると、シャクはまた別の霊の言葉を語り出しました。
今度は、それが何の霊であるか、直ぐに判りました。
武運拙く、戦場に敗れた顛末から、明らかに弟デックその人と、誰もが合点しました。
シャクが弟の死体のそばに茫然と立っていた時に、秘かにデックの魂が兄の中に忍び入ったのだと人々は考えました。
それまでは、彼の最も親しい肉親、及びその右手のことなので、彼にのり移るのも不思議はありませんでした。
しかし、今度はおよそシャクとは関係のない動物や人間達の言葉を語り始めたのです。
今までも、憑きもののした男女はいましたが、そんなに種々雑多なものが一人の人間にのり移った例はありませんでした。
ある時は、この部落の下の湖を泳ぎ廻る鯉がシャクの口を借りて、生活の哀しさと樂しさとを語りました。
ある時は、トオラス山の隼が、湖と草原と山脈と、その向うの鏡のような湖との雄大な眺望について語りました。
草原の牝狼が、冬の月の下で飢えに悩みながら、一晩中凍った土の上を歩き廻る辛さを語ることもありました。
人々は珍しがつてシャクの話をを聞きに来ました。
そして不思議なことに、シャク自身も多くの聞き手を期待するようになっていました。
【転】狐憑 のあらすじ③
シャクの聴衆は次第にふえて行きましたが、ある時彼等の一人がこんなことを言いました。
シャクの言葉は、憑きものがしゃべっているのではないぞ、あれはシャクが考えてしゃべっているのではないかと。
なるほど、そう言えば、普通の憑きもののした人間は、もっと恍惚とした忘我の状態でしやべるものでした。
シャクの態度にはあまり狂気じみた所がなく、その話は条理が立ち過ぎていたのです。
少し変だぞ、という者が増えてきました。
シャク自身も、普通の憑きものと違うようだと気が付いていました。
しかし、なぜ自分が奇妙な仕草を幾月にも続けて、飽きもしないのか、自分でも解らないのでした。
元来、空想的な傾向をもつシャクは、自分の想像の中で、自分以外の人に乗り移ることの面白さを覚えたのでした。
次第に聴衆が増え、彼等の表情が、安堵の・恐怖の色を浮べるのを見るにつけて、この面白さは抑えきれぬものになったのです。
空想物語の構成は日に日に巧みになっていきました。
若い者達がシャクの話に聞き惚れて仕事を怠るのを見て、部落の長老連がにがい顏をしだしました。
彼等の一人は、シャクのような男が出たのは不吉の兆しだと言いました。
この長老が、家の印として豹の爪をもつ・最も有力な家柄の者だったので、この老人の説は全長老の支持する所になりました。
彼等は祕かにシャクの排斥を企み始めたのでした。
そのころ、シャクの物語は、周囲の人間社会を題材にするようになっていました。
ある日、脱毛期の禿鷹の樣な頭をしているくせに若い者と美しい娘を張合つて惨めに敗れた老人の話をした時、聽衆がドツと笑いました。
あまりに笑うので、その理由を尋ねると、例の長老が同じ樣な惨めな経験をしたという評判だからだと答えるのでした。
【結】狐憑 のあらすじ④
長老は腹を立て、計をめぐらせました。
最近に妻を寢取られた一人の男がこれに加わりました。
シャクが自分にあてこする樣な話をしたと信じたからです。
二人は手を尽くして、シャクが常に部落民としての義務を怠っていることに、みんなの注意を向けようとしました。
それでも、人々はシャクの話の面白さに惹かれていたので、働かないシャクにも冬の食物を分け与えました。
厚い毛皮の陰に北風を避けて、彼等は冬を越しました。
春になり、シャクも野に出まっしたが、眼の光も鈍く、ぼけたように見えました。
人々は、彼が物語をしなくなつたのに気が付きました。
憑きものは落ちたけれど、シャに以前の勤勉さがることはありませんでした。
そんなころ、丁度雷雨季がやってきました。
彼等は雷鳴を最も忌み、恐れます。
狡猾な老人は、占い師を牛角杯二個で買収して、シャクの存在と、最近の頻繁な雷鳴を結び付けるのに成功しました。
そしてシャクは、翌日、祖先伝来のしきたりに従って処分されました。
湖畔では、焚火を囲んで盛大な饗宴が開かれていました。
大鍋の中では、羊や馬の肉に交つて、哀れなシャクの肉もふつふつ煮えていました。
物があまり豊かではないこの地方の住民にとって、病気で倒れた者のほか、全ての新しい死体は食用に供せられるのでした。
ホメロスと呼ばれた詩人が、美しい歌を詠み始めるよりもずっと以前に、こうして一人の詩人が喰われてしまったことを、誰も知らないのでした。
狐憑 を読んだ読書感想
中島敦の小作品である狐憑は、太古の昔を舞台としたロマンあふれる作品です。
この作品には教訓めいたものは一切なく、はるか昔にあった出来事が淡々と描かれているだけです。
詩人という職業、もしくは詩というものが認識される以前に、とある集落で起こった事件。
この事件が読者に残すのは、何とも言えない読後感です。
弟の死にショックを覚えたことを契機に、ストーリーテリングの面白さに目覚める主人公のシャク。
物語を作ったり、物語を語ったりすることに、価値のなかった時代に、その楽しさを発見したシャク。
そのことが、どのような価値を持つのか、そして人々にどのような影響を与えうるものなのか、そんな無限の可能性の片鱗を感じながらも、歴史の渦の中でひっそりと死んでいきます。
シャクを死に追いやった老人が悪いというわけでもなく、村人に想像の話をしたシャクが悪いわけでもありません。
ただただ、人間が詩や物語というものを発明する過程で、人知れず死んでいった偉大な詩人が無数にいたのではないかと、そんな雄大な想像をさせてくれる作品なのです。

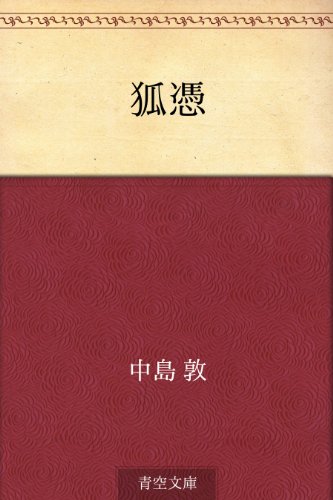
コメント