著者:中島敦 1942年12月に筑摩書房から出版
名人伝の主要登場人物
紀昌(きしょう)
趙の邯鄲の都に住む男。 天下第一の弓の名人を志す。
飛衛(ひえい)
当代きっての弓の名手。 百歩を隔てて柳葉を射て、百発百中の達人。
甘蠅老師(かんようろうし)
年齢は百歳は超えていると思われる隠者。 飛衛を大きくしのぐといわれる弓の大家。
名人伝 の簡単なあらすじ
ある日、趙の邯鄲の都に住む紀昌という男が、天下第一の弓の名人になるという志を立てました。
まず手始めに、自分の師匠となるべき人を探したところ、当代きっての弓の名手・飛衛がよかろうとなりました。
紀昌は飛衛のもとで修業に励み、大変な努力の末に、ついには師匠の飛衛と並ぶまでになりました。
紀昌は、天下第一の名人となるべく、師匠の飛衛に弓の勝負を挑みます。
しかし、勝敗はつかないままに、師弟は互いに認め合うのでした。
そこで師匠の飛衛が言うには、これ以上の上達を望むなら、甘蠅老師を教えを乞うべきという事でした。
名人伝 の起承転結
【起】名人伝 のあらすじ①
ある日、趙の邯鄲の都に住む紀昌という男が、天下第一の弓の名人になるという志を立てました。
まず手始めに、自分の師匠となるべき人を探したところ、当代きっての弓の名手・飛衛がよかろうとなりました。
飛衛は、百歩を隔てて柳葉を射て、百発百中の達人とのことです。
紀昌は、はるばる飛衛をたずねていき、その門下に入り弟子となりました。
飛衛が弟子に命じたことは、まず「瞬しないことを学べ」でした。
紀昌は家に帰って、妻の機織台の下に潜もぐり込こんで、仰向にひっくり返りました。
眼とすれすれに機躡が忙しく上下往来するのをじっと瞬かずに見詰みつめていようという工夫でした。
紀昌は、来る日も来る日もこのおかしな恰好かっこうで、瞬きしない修練を重ねました。
二年後には、あわただしく往返する牽挺がまつげをかすめても、瞬くことがなくなったのでした。
彼はようやく自信を得て、師匠の飛衛にこれを告げに行きました。
それを聞いて飛衛は言いました。
「瞬かないだけでは射を授けるに不足しています。
次は、視ることを学びなさい。」
「小を視ること大のごとく、微を見ること著のごとくなったならば、私に再び報告しなさい」と。
紀昌は再び家に戻り、肌着の縫目から虱を一匹探し出し、これを自分の髪の毛でつなぎました。
そして、それを南向きの窓に置いて、終日睨んで暮らすことにしました。
毎日毎日彼は窓にぶら下った虱を見詰めると、十日余り過ぎたころにほんの少しながら大きく見えて来ました。
その虱が何十匹となく取り換えられて、三年の月日が流れました。
ある日ふと気が付くと、窓の虱が馬のような大きさに見えていました。
【承】名人伝 のあらすじ②
これはしめたと、紀昌は膝を打ち、初めて表へ出ました。
すると、彼は我が目を疑いました。
人は高塔でした。
馬は山でした。
豚は丘のようでした。
小躍りしながら家にとって返した紀昌は、再び窓際の虱に立向い、燕角の弓に、朔蓬の矢をつがえて、これを射てみました。
すると、矢は見事に虱の心臓を貫いて、しかも虱を繋いだ毛さえ切れぬのでした。
紀昌は早速、師匠の許に赴いて、これを報告しました。
すると、飛衛は胸を打ち、初めて「出かしたぞ」と、紀昌を褒めました。
それから飛衛は、すぐに射術の奥儀秘伝を、あますところなく紀昌に授け始めました。
目の基礎訓練に五年もかけた甲斐があってか、紀昌の腕前の上達は、驚くほどに速いものでした。
奥儀伝授が始まってから十日後、試しに紀昌が百歩を隔てて柳葉を射たところ、既に百発百中でした。
二十日後には、いっぱいに水の入った盃を右肘の上に乗せて、剛弓を引いても、狙いが狂うことはありませんでした。
そのうえ、杯中の水も微動だにしないのでした。
一か月後には、百本の矢で速射を試したところ、第一矢が的にあたれば、続いた第二矢は第一矢の「やはず」にあたって突き刺ささり、さらに間髪を入れずに第三矢の鏃が第二矢の「やはず」に食い込むのでした。
これが延々と続き、矢は地におちることがないままに、百本の矢が一本の矢のように連なりました。
そばで見ていた師匠の飛衛も、思わず「よし!」と言ったほどです。
二か月後には、家に帰って妻と喧嘩をした紀昌が、これを脅かすために、妻の目を狙って射ました。
その矢は、妻の睫毛三本を射切って、かなたへ飛び去りましたが、射られた本人は一向に気づかず、まばたきもしないで亭主を罵ののしり続けたそうです。
【転】名人伝 のあらすじ③
もはや師から学び取るべきものが無くなった紀昌は、ある日、ふと良からぬ考えを思いつきました。
彼がその時考えたのは、次の通りでした。
「今や弓をもって自分に匹敵すべき者は、師匠の飛衛以外にいない。」
「天下第一の名人となるには、飛衛を越えねばならない。」
ひそかに機会をうかがっているうちに、ある日偶然、向うから一人で歩み来る飛衛に出会いました。
とっさに意を決した紀昌が矢を取って狙いをつけると、その気配を察して飛衛もまた弓を執とって応じました。
二人がたがいに射れば、矢はその度に道の半ばでぶつかり、地に墜ちました。
地に落ちた矢が塵ひとつあげなかったのは、両者の技がいずれも神がかっていたからでしょう。
そしてついに飛衛の矢が尽つきる時が来ましたが、紀昌の方はなお一矢を残していました。
これは得たりと、勢いこんで紀昌がその矢を放つと、飛衛は野茨の枝えだを折り取り、その棘の先端をもって鏃を叩き落しました。
ついに望みが遂げられないことを悟った紀昌の心に、成功したら生じなかった道義的慚愧の念が沸き起こりました。
飛衛の方は、危機を脱した安堵と、自分の伎倆への満足が、敵への憎しみを忘れさせました。
二人は互いに駆け寄り、野原の真中で抱き合い、美しい師弟愛の涙を流しました。
しかし、再び弟子が同じ企たくらみを抱いては危いと思った飛衛は、紀昌に新たな目標を与あたえて気を紛らわせようと考えました。
彼はこの危険な弟子に向って、次のように言いました。
「もはや、教えるべきことは教えた。
君がさらに奥義を極めたいと望むなら、甘蠅老師という大家の教えを乞いなさい。」
「老師の技に比べれば、我々の射の技術など子供の遊びです。」
【結】名人伝 のあらすじ④
紀昌はすぐに西に向って旅立ちました。
一か月後、彼はようやく目指す場所にたどり着きました。
気負い立つ紀昌を迎えたのは、柔和な目をした、ひどくよぼよぼの爺さんで、年齢は百歳を超えているようでした。
紀昌は私の技を見てもらいたいむねを述べると、相手の返事も待たずに弓を外して手に取りました。
そして、矢をつがえると、空高くを飛び過ぎて行く渡り鳥の群に向って矢を打つと、たちまち五羽の大鳥が落ちて来たのです。
一通り出来るようじゃな、と老人が穏やかに言いました。
だが、それは所詮「射之射」というもの、あなたはいまだ「不射之射」知らぬと見えるというのです。
老隠者は、そこから二百歩ばかり離た絶壁の上まで連れて来て、見えざる矢を無形の弓につがえて放ちました。
すると、鳥は羽ばたきもせず空中から石のように落ちてきたのです。
結局は九年間、紀昌はこの老名人の許にとどまりました。
九年たって山を降りて来た時、人々は紀昌の顔つきの変化に驚きました。
以前の負けず嫌ぎらいな表情は影をひそめ、なんの表情も無い、木偶のような、愚者のような容貌に変わっていたのです。
しかし、飛衛は、この表情を一見すると感嘆して叫びました。
これでこそ初めて天下の名人だ。
我らの、足下にも及ぶものでないと。
それから月日は流れ、紀昌が死ぬ一二年前のことです。
老いた紀昌が知人の許に招かれて行ったと際に、その家で一つの器具を見て尋ねました。
「確かに見憶えのある道具だが、どうしてもその名前が思出せぬし、その用途ようとも思い当らない。」
「それは何と呼ぶ品物で、また何に用いるのでしょうか?」主人は、客が冗談を言っていると思って、笑いました。
しかし、老紀昌は真剣に再び尋ました。
主人は驚きました。
彼は、相手が冗談を言っているのでもなく、気が狂っているのでもなく、また自分が聞き違えをしているのでもないことを確かめると、言いました。
「古今無双の射の名人のあなたが、弓を忘れたのですか? 弓という名も、その使い途も!」その後しばらくは、邯鄲の都では、画家は絵筆を隠かくし、楽人は瑟しつの絃を断ち、工匠は規矩を手にするのを恥じたということでした。
名人伝 を読んだ読書感想
中島敦の代表作のひとつでもある名人伝は、非常に興味深い小説です。
この物語の言わんとしていることが、読む人によって変わるからです。
さらに言えば、この小説を読んだと時の年齢や心境によっても変わるかもしれません。
そんな不思議な魅力と読後の余韻を持った小説といえるでしょう。
中島は、この小説において、教訓めいたものを明言することを避けているようにも思えます。
天下第一の弓の名人になることに、真剣に取り組んでいる姿はビシビシ伝わってきますし、名人芸のすさまじさの描写も驚くべきものです。
しかし、それを習得するための修練の方法や、鍛えた名人技で妻のまつ毛をいてみたり、突然打ち合う師弟の描写など、ところどころに登場人物達をからかうかのようなコミカルな部分があります。
結局のところ、最後まで名人というものが何かはわからないのですが、名人をありがたがった人達や、その名人のあり方を形だけマネする人々の描写で話は幕を閉じるのです。
この話が言わんとしていることは、名人としての佇まいや考え方のことなのか、それとも名人を風刺した、世間の滑稽さなのか、その真意を知るには、原典にまでさかのぼる必要があるかもしれません。

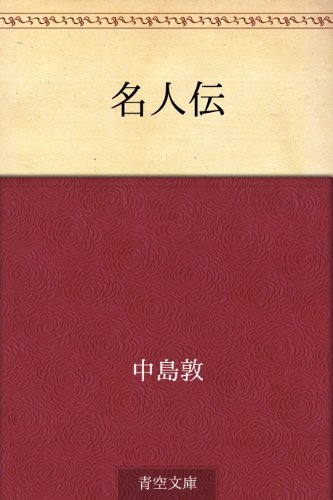
コメント