著者:谷崎潤一郎 1918年5〜7月(新聞掲載)に大阪毎日新聞、東京日日新聞から出版
白晝鬼語の主要登場人物
園村(そのむら)
精神病の遺伝があると自称している男。
高橋(たかはし)
作中の語り手である〈私〉。小説家。園村の数少ない友人。
纓子(えいこ)
芸者風の謎の美女。
村松(むらまつ)
子爵。行方不明になっている。
白晝鬼語 の簡単なあらすじ
〈私〉の友人の園村は、あることから殺人が行われることを知りました。
彼に誘われて、〈私〉は深夜に犯行の現場を見に行きます。
隙間からのぞくと、そこには妖しい美女がいて、ついいましがた、男を絞殺したばかりのようでした。
現場からはなれた園村は、あの美女と交際したいと言いだします。
そうして実際に美女との交際が始まり、やがて、仲間の青年までも自分の屋敷に引き込むことになったのです。
絶交を言い渡した〈私〉のもとに、園村から「遺書」と書かれた手紙が届いたのは、それからしばらくのちのことでした……。
白晝鬼語 の起承転結
【起】白晝鬼語 のあらすじ①
精神的に不安定なところのある友人の園村が、ある日、〈私〉に電話してきました。
殺人が行われるので、いっしょに見に行こう、という用件でした。
〈私〉は依頼されていた小説をなんとか仕上げて、園村の家を訪ねました。
園村はこんなふうに事情を説明してくれました。
一昨日の晩、彼は活動写真を見に行きました。
すると、彼の前の席にいた三人組の男女が、奇妙なことをしたというのです。
その三人組は、若い婦人、その亭主らしき男、亭主の友人らしき男、の順に並んでいます。
見ていると、夫人と、反対側の男が、真ん中の男の背中で手をつないで、指文字でやりとりを始めました。
「クスリハイケヌ、ヒモガイイ」などと文字を交しています。
そのあと、女が男へ紙を渡しました。
男はその紙を持ってトイレに立ち、戻ってくると紙を丸めて床に捨てました。
園村がその紙を拾い、広げてみると、暗号文が書かれています。
園村は、ポオの探偵小説にある暗号と同様の方法で、それを読み解きました。
暗号文は英文だったのです。
そこからさらに日本語に翻訳すると、内容は殺人予告のようです。
犯行の日時は、今夜半、午前一時三十六分。
犯行の場所については、暗号文の「ネプチューンの北に一片の鱗あり」という一節から、向島の水神のあたりに鱗の印をつけてある、と解釈できます。
昨日、園村は向島の水神のあたりを探したのですが、鱗の印は見つけられなかったそうです。
もしかすると、今日、犯行の直前に印をつけるのかもしれません。
〈私〉は、園村といっしょに、車に乗って向島へ向かいました。
【承】白晝鬼語 のあらすじ②
夕方の六時から八時にかけて、〈私〉は園村に引きずりまわされ、水神の近くを探したのですが、鱗の印は見つかりませんでした。
〈私〉は園村を説得して帰宅しました。
ところが、夜中の十二時を過ぎたころ、園村が自宅へやってきたのです。
暗号文の「ネプチューン」というのは、水神ではなく水天宮だと気づいた彼は、あらためて向島へ行き、水天宮の北側の新路で鱗の印を見つけた、と言います。
〈私〉は園村に強引に連れ出されました。
〈私〉たちが目標の家に着いたときには、暗号文で予告された時刻を少しすぎていました。
そこは小さな平屋の家で、隙間や穴がたくさんあります。
〈私〉たちは節穴から中をのぞきこみました。
初め〈私〉が見たのは、婦人の白いうなじでした。
その髪や着物から、女は芸者ではないか、と〈私〉は想像しました。
女が少し位置を変えます。
壁際に角刈りの青年が立っていて、そばに三脚に乗せたカメラがあるのが見えます。
また、女の膝には、別の男が膝枕している様子です。
じきに、膝枕している男が死んでいるのがわかりました。
その首には、女のしごきのような真紅の紐が巻きついています。
園村が解読した暗号文のとおり、たった今殺人が行われたようです。
この凄惨な現場で、女の妖艶な美しさはきわだっています。
角刈りの青年が、「姐さん」と女に呼びかけます。
女は男の死体を部屋の中央へと引きずっていき、死体を膝枕させた状態で、写真に撮らせました。
それから青年は何かの薬品を調合すると、大きな金だらいの中に入れ、水を満たしました。
女が死体をたらいの中に入れます。
「明日の朝までに溶ける」と青年が言うのに対して、「こんなに太っているから、いつかの松村さんのようなわけにはいかない」と女が言い返します。
調合した薬は、死体を溶かす薬のようです。
今夜の作業が終わり、女たちは寝ることに決めたようです。
女が金だらいのあるこちらの部屋に布団を敷き、青年はとなりの部屋に布団を敷いて、眠りました。
〈私〉たちは物音をたてないようにして、現場をはなれました。
【転】白晝鬼語 のあらすじ③
現場をはなれた〈私〉たちは、タクシーをつかまえて乗りこみみました。
園村はだんだんと元気になり、目には異常な光がやどっています。
発狂しているとまでは言わないまでも、精神的に異常をきたしているように感じられます。
園村は、今見てきた事件のことを語ります。
園村が見たとき、男はすでに死んでいました。
女は、男の頭を膝枕して死んでいることを確認すると同時に、念のためにもう一度首を絞めていたのだろう、というのが園村の考えです。
それにしてもあの女は美しかった、と彼は言います。
あれは芸者風だが、芸者ではない、ものすごい獣のような残忍さと強さが表情にあらわれていて、造りの美しさの上に、すごみを加えていた、と園村は評価します。
なぜそんなにあの女の美しさにこだわるのか、〈私〉には不思議でした。
実は園村はあの女と知り合いになりたいのだ、と言うのです。
彼はこのところすっかり生活に興味がなくなっており、刺激がほしいのでした。
〈私〉が女の正体について問うと、園村は次のように自分の考えを語りました。
——あの女は悪党の一味ではないか。
「松村」という名前が出てきたが、ふた月ほど前の新聞記事で行方不明になったとあった、子爵の松村氏のことだろう。
あの女は、松村氏が京都へ行く汽車の中で知り合いになり、殺して、あの液に付けて溶かしたのだろう。
また、今日殺されたのは、悪党の一味で、女の亭主ではないか。
——そういう推理を述べたあと、園村は言います。
あの女は、これまでに何人も殺してきた異常快楽殺人犯ではないか、と。
そうして、そんな恐ろしい殺人狂であるにもかかわらず、あの女こそが、長い間園村が恋焦がれてきた鬼であり、彼女こそが彼の孤独をなぐさめてくれるのだ、と言うのです。
園村はすっかりあの女に首ったけなのでした。
【結】白晝鬼語 のあらすじ④
〈私〉は園村の身を心配し、何度か彼の家を訪ねました。
そのたびに留守でしたが、ようやく一週間目に会うことができました。
すると、あの女が家に来ていると言います。
〈私〉は庭の植込みからこっそりと彼女の姿を見ることにします。
女の名前は纓子というそうです。
〈私〉が陰からのぞくと、園村と纓子はかなり親しげに話しています。
女は、自分の身の上は明かせないので、そのつもりで付き合ってほしい、と言っています。
さて、それからひと月後、〈私〉は三越の陳列場で園村と纓子を見かけました。
驚いたことに、あの角刈りの青年もいっしょにいたのでした。
〈私〉は纓子の留守をねらって園村の家へ行き、別れるように忠告しました。
が、園村は耳を貸しません。
〈私〉は絶交を言い渡しました。
それからさらにひと月後、園村から手紙が届きました。
冒頭に「これを遺書と思ってほしい」と書いてあるではありませんか。
手紙によると、園村はもうすぐ纓子に殺される、とあります。
というのも、園村は全財産を纓子に巻きあげられてしまったそうです。
纓子はお金目当てで交際に応じていたので、金の切れ目が縁の切れ目で、園村が邪魔になっているのでした。
また、彼らの正体を園村が知っていることに、彼らが感づいたことも、殺害の動機となるようです。
園村は今夜十二時五十分に、例のところで殺されるので、〈私〉にその様子を見てほしい、と書いています。
〈私〉はその時刻に向島の例の家へ行き、女が園村を殺すのを見ました。
それから二日目、園村の死体の写真が送られてきました。
写真の裏に書かれていた頼みごとを片づけるために、〈私〉は園村の家に出かけていきました。
ところが、彼の家に行ってみると、なんと園村はぴんぴんしているではありませんか。
園村は説明します。
以前、向島で自分たちが見た事件は、纓子たちが園村の興味をひきつけるためにうった狂言でした。
松村子爵のことは、新聞で失踪を知ったので、さも殺したかのように言っただけだったのです。
そして親密な仲になった後、園村は纓子に、全財産をやるから自分を殺してほしい、と頼みました。
さすがにそこまではできない、と拒否され、では殺すまねでもいいから、と頼みこんんで実行してもらったのが、先日の園村殺害の真相なのでした。
白晝鬼語 を読んだ読書感想
タイトルの「白晝鬼語」は「はくちゅうおにがたり」と読むようです。
本作をひとことで言うなら「怪奇探偵小説(の先駆的な作品)」ということになるでしょうか。
奥歯にものの挟まったような表現になったのは、この作品が探偵小説としては未熟な面があるからです。
たとえば、前半で、ポオの作品を思わせる暗号が出てきます。
探偵小説というからには、この暗号が論理的に解き明かされなければなりません。
しかし、作中では、推理なしで、いきなり解答が提示されているのです。
ただし、これは時代背景を考えると、無理もない気がするのです。
江戸川乱歩が日本で最初の本格的な探偵小説「二銭銅貨」を発表するのは、本作から五年後の大正十二年のことです。
まだ読者の側も、作家の側も、論理的な探偵小説に対する心構えができていない時期でした。
そこへ探偵小説を披露するというのは、例えて言うと、オペラを聞いたことのない人々にオペラを聞かせるようなものです。
いきなり論理的な推理を展開してみせても、読者はついてこない恐れがありました。
したがって、ミステリの要素だけをちょっと見せて、読者の興味をひきつけるのがよい、と著者は考えたのではないでしょうか。
ただし、その一方で、「異常快楽殺人犯」というきわめて今日的な犯罪者像を掲示している点は、大いに注目すべきだと思います。
そういった犯罪者の内面については、まだ探偵小説慣れしていない読者も興味を示してくれるだろう、との読みもまた、著者にはあったに違いありません。

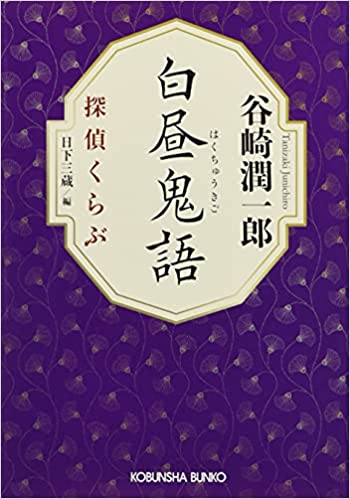
コメント