著者:谷崎潤一郎 1919年1〜2月(新聞掲載)に朝日新聞社(新聞掲載)から出版
美食倶楽部の主要登場人物
G伯爵(じーはくしゃく)
美食倶楽部の会長・幹事的な役割をはたす男。倶楽部の会員のなかで一番若く、一番胃腸が強い。
(美食倶楽部のメンバー(びしょくくらぶのめんばー))
暇をもてあまし、美食を食べることが生きがいのサークル。G伯爵を含めて五人。作中にG伯爵以外の名前は出てこない。
(支那人(しなじん))
支那料理を食するグループのなかへ、G伯爵を案内してくれた支那人。作中に名前はでてこない。
陳(ちん)
支那料理を食するグループの会長
美食倶楽部 の簡単なあらすじ
お金を持った暇人の五人が集まり、美食を追及する美食倶楽部というサークルのようなことをやっています。
その美食倶楽部の幹事役のG伯爵が、ある夜、ふとした縁で、浙江会館で開かれている支那人の宴会に入りこみます。
そこでは支那人による本物の支那料理が食されていました。
G伯爵は、どうか自分にも食べさせてほしいと頼み込んだのですが、会長の陳さんから拒絶されます。
あきらめきらないG伯爵は、隅っこに隠れて、その夜のメインディッシュの様子を覗き見させてもらいます。
そうしたことがあって、その後、G伯爵が美食倶楽部に提供する美食は、大きく様変わりしたのでした。
美食倶楽部 の起承転結
【起】美食倶楽部 のあらすじ①
美食倶楽部という、わずか五人のサークルがあります。
メンバーはみな金持ちで、暇を持て余し、博打を打つか、女を買うか、うまいものを食うしかない男たちです。
とりわけ、おいしいものを食べることには目がなく、みなぶくぶくと肥え太り、胃拡張となっているのに、美食を追及してやみません。
彼らは市中の有名な料理店はすべて食べつくし、飽きてしまい、「今度はなにを食べたらいいのか」と、贅沢な悩みを抱えているのでした。
そのため、スッポンを食べるためだけにわざわざ京都へ行き、鯛茶漬けを食べるために大阪へ行き、河豚料理を食べるために下関へ行くしまつでした。
そんな美食倶楽部の幹事的な役割を担っているのが、G伯爵です。
五人のなかで一番年が若く、一番の金持ちです。
彼は四六時中料理のことを考えています。
食べれば食べるほど美味が舌にからんできて、胃腸が破裂してでも食べ続けずにはいられない、そんな料理を作りだしたいと思っているのです。
さて、ある晩のことです。
美食倶楽部でありきたりの美食をとったあと、G伯爵は散歩に出ました。
表通りをずっと歩いていったところで、前から来た二人の支那人とすれ違いました。
G伯爵の鼻は、二人が紹興酒の匂いを発散させているのを、敏感に嗅ぎ取ります。
どうやら二人は支那料理を食べてきたようです。
このあたりに支那料理の店はなかったはずですが、もしかすると、新しい店ができたのかもしれません。
耳をすますと、向こうの路地のほうから、大勢の人の声や拍手の音が聞こえてきます。
宴会のようです。
きっとその宴会で支那料理がふるまわれているのでしょう。
G伯爵はふらふらとそちらへ歩いていきました。
しばらく行くと、電灯を煌々とつけた三階建ての木造の西洋館にたどりつきました。
三階のほうから拍手と胡弓の音が聞こえてきます。
G伯爵は胡弓の奏でる音楽を聞きながら、支那料理を連想するのでした。
【承】美食倶楽部 のあらすじ②
G伯爵は舌なめずりして、ぜひこの店の料理を食べてみたいと思い、中に入ろうとしました。
しかし、扉は内側から締まりがしてあるらしく、開きません。
そのときG伯爵は、門柱に「浙江会館」という看板がかかっているのを見つけたのです。
どうやらここは料理屋などではなく、日本に在留する浙江省の支那人の倶楽部だと気づきました。
とはいえ、鎧戸の隙間からは、なんともおいしそうな匂いが漏れ出てきます。
こういう支那人の倶楽部であれば、日本にある「支那料理店」が出すまがいものの「支那料理」ではなく、本物の支那料理が食べられるに違いありません。
「なんとかして、この家の料理を食べさせてもらう方法はないものか」と、G伯爵は入口のところでうろうろします。
三十分もそうやってうろうとした後、ひとりの大柄な支那人が鎧戸を開けて出てきました。
彼はよろけてG伯爵に肩をぶつけてしまい、詫びを入れます。
G伯爵は彼に、自分は支那料理が大好きでさっきからうろうろしていたことを打ち明け、中に入れてもらえないか、と頼みました。
二人の話が階上にも届いたようで、何人かの支那人が出てきて、伯爵を中へ入れてくれました。
三階へのぼると、そこは宴会場となっており、コック場の煙、煙草の煙、水蒸気などのせいで、人の顔もよく見通せないほど空気が霞んでいます。
よく見ると、向こうのテーブルでは、豚の胎児の丸煮が食べられており、そっちのテーブルではツバメの巣が食べられています。
G伯爵は、壁の隅によりかかっている太った紳士の前へと連れていかれました。
紳士の両隣には、纏足の美女が椅子に座っています。
ひとりは膝の上に胡弓を乗せており、先ほどの音楽は彼女が奏でていたようです。
G伯爵の手を引いてきた男が、「これが会長の陳さんです」と紳士を紹介しました。
【転】美食倶楽部 のあらすじ③
G伯爵の手を引いてきた男は、会長と志那語で何事か話しました。
話が終わると、会長はG伯爵に言いました。
「支那料理が好きならばご馳走してもよいのだが、ここの料理はおいしくない。
それに、コック場がしまったので、次の機会にしてほしい」、と。
G伯爵が、余り物でよいから食べさせてほしい、と食い下がっても、「彼らは大食いだから余らない。
そもそも、余り物を出すなど失礼だ」と、取り合ってくれません。
引率の男は、G伯爵を出口のほうへ連れていきました。
「ここでは会長が権力を持っているので、許可が出なければどうしようもない」と男は言います。
また、「もしかすると会長はG伯爵を疑っているのかもしれない」とも言います。
ここは入場者の人選がやかましくて、誰でも入れるものではないそうです。
というのも、会長は美食を食べるばかりでなく、作るのにも秀でているのですが、その料理は常識を超えている面があります。
材料はありとあらゆるもの、上は人間から下は昆虫にいたるまでが料理に使われます。
食器も皿や椀といった普通のものばかりではなく、おまけに、食器の中に料理が盛られているばかりではありません。
食器の外に塗られたり、食器の上に噴水のように噴き出すこともあります。
そんなとんでもない料理を出すものですから、人選は厳密になされるのだと、男は言います。
そういうわけで、会長に逆らってG伯爵に食べさせることはできないけれども、こっそりと見ているくらいは許されるだろう、と男はG伯爵を隅の方へ連れていきます。
そこは衝立で仕切られた場所です。
そこでアヘンを吸うのだそうで、異様な匂いがします。
男は衝立に開いた穴から、これから出されるメインディッシュを覗くようにと、G伯爵に勧めるのでした。
【結】美食倶楽部 のあらすじ④
その晩以来、G伯爵が美食倶楽部に提供する料理は、大きく変わりました。
それはベースは支那料理なのですが、これまでに例のない料理だったのです。
たとえば、鶏粥魚翅(けいしゅくぎょし)を取り上げてみましょう。
どんよりした汁を口に入れると、葡萄酒のような甘みが口の中いっぱいにひろがります。
「甘ったるいばかりじゃないか」と文句を言おうとした会員が、そこで表情を一変させます。
甘ったるさばかりだった口の中に、ふいに鶏粥と魚翅の味とが舌に染みこんできたからです。
そればかりか、すでに胃の中に入った汁が、ゲップとなって出てくると、そこには間違いなく鶏粥と魚翅の味がついていて、口の中はそれらの味が充満するのでした。
G伯爵は言います、「これは料理というより魔術だ。
だから、この作り方は自分の秘伝とする権利がある」と。
そうして、あの夜の浙江会館でのことは、引率してくれた支那人との約束を守って口外しないのでした。
G伯爵の美食の魔術は、それ以降、いよいよ不思議な領域へ入っていきます。
美食倶楽部の面々は、単に舌によって味わうだけではなく、五感すべてを使って、言い換えると、体中を舌として味わうことが求められるのでした。
ひとつの例として、火腿白菜(かたいはくさい)をあげましょう。
火腿といいうのはハムのことです。
美食倶楽部の面々は、真っ暗な部屋のなかで、四隅に散って直立させられます。
彼らが寒さと暗闇で不安になった頃、女性が忍び寄ってきます。
女性は指を会員の口の中に入れ、舌をなぶります。
唾があふれてきます。
その唾がいつの間にかハムの味に変わっています。
女性の指だと思ったものがいつの間にか白菜の茎に化けています。
かじると、やはり白菜です。
にもかかわらず、女性の指はそのまま指なのです。
それはあたかも指と白菜の合の子のような物質なのでした。
会員が白菜の茎を存分にかじり終えると、女性の指はやはりちゃんとそのまま指で、その指が会員の口の中を掃除して、この料理はおしまいとなるのでした。
さて、それ以降も、G伯爵の料理はますますエスカレートしていきます。
美食倶楽部の会員たちは、もはや美食を「味わう」のではなく、「狂」っているとしか言えないのでした。
美食倶楽部 を読んだ読書感想
なんともはや、粘体質のものすごい小説だなあ、というのが一読しての偽らざる感想です。
オノマトペを用いるなら、「ねっとり」とか「ねちょねちょ」という言葉が当てはまります。
ストーリーはきわめて単純です。
美食倶楽部の幹事をしているG伯爵が、本物の支那料理を食べる集まりを見たことで、自分の料理を一変させた、というものです。
この作品のウリは、ですからストーリーにあるのではなく、すさまじいまでの描写力で書かれた、「美食」を味わうときの「官能」にあります。
たとえば、最後のほうに出てくる「火腿白菜(かたいはくさい)」を味わうものすごさといったらありません。
暗闇の中で、女性の指に口の中を蹂躙されていくのです。
なんとエロティックなことでしょうか。
エロティシズムと美食の融合だなあ、と感じます。
性欲と食欲は、ともに人間の本能ですから、親和性が高いのかもしれません。
それにしたって、生半可な筆力でできることではないと思います。
谷崎潤一郎が「耽美派」と言われるわけが、この一作をもってしても、よくわかる気がするのでした。

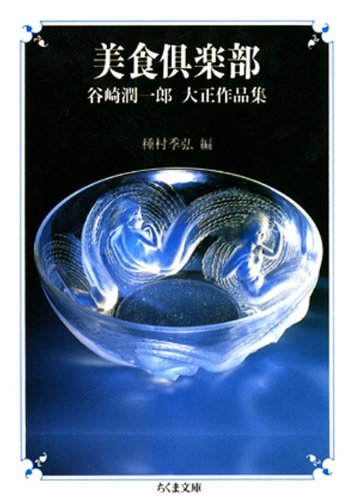
コメント