著者:井伏鱒二 1956年12月に角川から出版
屋根の上のサワンの主要登場人物
私(わたし)
主人公。撃たれた雁を保護し、サワンと名付けて家で飼い始める。サワンが逃げられないように風切羽根を短く切っている。
サワン(さわん)
雁。撃たれて怪我をしていたところを保護される。
雁の群れ(がんのむれ)
サワンの鳴き声に応じ、サワンを迎えにやってくる。
屋根の上のサワン の簡単なあらすじ
ある日、私は沼池の岸で一羽の雁を見付けました。
雁は鉄砲で左の翼を撃たれており、飛べずに苦し気に鳴いていました。
私は雁を家に連れ帰って治療をした後、雁にサワンと名付け、逃げられないように風切羽根を短く切り、家で飼う事にしました。
しかし一年後、サワンに異変が起こります。
夜な夜な屋根に登り、雁の群れに向かって騒々しく鳴くのです。
私はサワンが逃げてしまうのを恐れ、サワンを必死で引き留めましたが、サワンは鳴くのを止めません。
私がサワンを群れに返す決心をした翌日、サワンは私の前から姿を消してしまいました。
屋根の上のサワン の起承転結
【起】屋根の上のサワン のあらすじ①
ある日、私は沼地の岸で、一羽の雁を見付けました。
猟師か悪戯な鉄砲撃ちに撃たれたのでしょう。
雁は左の翼に酷い怪我を負い、右の翼だけで必死に羽ばたいては、悲鳴のような鳴き声を上げていました。
私は雁にこっそり近付き、両手で持ち上げました。
両手に伝わる雁の羽毛や温もり、意外な重みは、私の屈折した心を慰めてくれるようでした。
私は雁を元気にしてやろう決心しました。
そこで、家に連れ帰り、暴れる雁の両足を縛り、押さえ、怒鳴りつけながら治療を施しました。
手術用の道具などありません。
治療の結果がどうでるかは知れませんでしたが、小刀で肉に食い込んだ銃弾をほじくり出し、傷口を洗い、消毒液を振りかけてやりました。
撃たれた傷口の様子から、雁が撃たれた状況を想像しました。
おそらく雁は、怪我が治るまで沼地の水草の中で休むつもりだったのでしょう。
そこに偶然、私がやってきたのでしょう。
言葉に言い表せないほど、屈託した気持ちで沼地を散歩していた私に。
私の親切心がわからない雁は、治療の間ずっと鳴き続けていました。
治療後は、暴れて傷口に障りがないよう、出血が止まるまで、雁を縛ったまま部屋に放っておきました。
疲れていた私は、隣の部屋で居眠りをしていました。
真夜中、けたたましい雁の鳴き声で目を覚ました私は、体を縛られたまま、首だけを電球の方へと伸ばして鳴こうとしている雁の姿を見ました。
雁は電球の明かりを、夜更けの月と見間違えたようでした。
【承】屋根の上のサワン のあらすじ②
すっかり傷が癒えて、雁は元気になりました。
私は雁にサワンと名付け、家で飼う事にしました。
庭で放し飼いにしていましたが、逃げられないように、両方の翼の風切羽根を短く切って、飛べないようにしました。
サワンは人懐こい鳥で、犬が飼い主に仕えるように、庭の木戸を開けて外出しようとする私の後をつけて来たり、夜更けになると家の周りを歩き回ったりしていました。
私もサワンを連れて、野道や沼地への散歩に出掛けたりしました。
名前を呼べば、サワンは眠そうな足取りで、私の後をついて来ました。
サワンは沼地を好んでいました。
水に滑り込み、短い翼で羽ばたいてみせたり、尾を振っては、水浴びに興じていました。
飽きない限り、呼んだところでサワンは水から上がってくる事はありません。
サワンは水面に浮かんでいるばかりではなく、水に潜る事も好んでいました。
時には水中に潜んでいましたが、沼地の水はよく澄んでいるので、私はサワンを見失わずにすんでいました。
私はサワンの水浴び中、草むらに寝転んで、自分自身の考えに耽っていました。
私はサワンの水浴びを見守るためではなく、自分自身の屈託した考えを追い払うために、沼地に散歩に出ていたのでした。
サワンは夜行性らしく、昼間は庭に放っておいても、廊下の下でうずくまってひたすら昼寝をしていましたが、夜になると庭の垣根を破ろうとしたり、木戸を飛び越えようとするのです。
私はサワンが逃げないよう、注意を払っていました。
【転】屋根の上のサワン のあらすじ③
やがて夏が過ぎ、秋になりました。
木枯らしが激しく吹き去った、ある日の夜更けの事です。
物思いに耽りながら火鉢で足袋を乾かしていた私は、サワンの甲高い鳴き声を聞きました。
静かな夜更けに響き渡る、物々しい鳴き声です。
私はサワンに注意しましたが、サワンは鳴き止みません。
外に出て見れば、サワンは家の屋根の上に立って、長い首を空高くへと伸ばし、できる限りの大声で鳴いています。
空には赤く汚れた歪な月が浮かんでいました。
そして、そんな月の前を横切るように、三匹の雁の群れが飛んでいたのです。
サワンは雁の群れと、話でもするかのように鳴き声を交わしていました。
雁の群れに向かって、自分も連れていってくれ、と叫んでいるかのようなサワンを見て、私は心配しました。
サワンが逃げ出してしまうのではないか、と。
彼らの会話を邪魔すべく、サワンに屋根から降りるように命令しましたが、サワンはいつもと違って言う事を聞きません。
雁の群れに鳴きすがるサワンを、私は庭木の枝を棒切れで叩きながら怒鳴り付けました。
しかし結局、サワンは私を無視し続けました。
雁の群れがいなくなってしまうまで、屋根の上から降りる事はなかったのです。
私は考えました。
サワンがまた屋根の上に登らないようにするためには、サワンの足を紐でもって、柱にくくり付けておかなければならないでしょう。
しかし私は、サワンが私の愛着を裏切って、遠い所へ逃げ去るはずがないと信じていたのです。
【結】屋根の上のサワン のあらすじ④
それからサワンは、月の明るい夜の明け方になると、屋根に登って甲高い声で鳴くようになりました。
そんなサワンに、雁の群れは微かな声で応えます。
その微かな声はまるで、夜更けが孤独に打ち負かされてもらす溜息のようでした。
ある夜、サワンはいつもより更に甲高く鳴きました。
ほとんど号泣に近い鳴き声でしたが、私は外に出ようとは思いませんでした。
屋根に登ったサワンは、私の言付けを守ろうとはしないからです。
私は部屋の中で、サワンが早く鳴き止んでくれる事を願ったり、明日からはその羽根を切らないでやって、自由に解き放ってやらなければ、と考えていました。
私はサワンの鳴き声から逃げるように眠りましたが、サワンが空を仰いで号泣する姿は、夢にまで出てくるのでした。
そして、私は決心しました。
明日の朝になったら、サワンの翼に薬を塗って、短く切った風切羽根を早く元通りにしてやろうと。
新しい羽根があれば、サワンは望むままに空高くへ飛んでいけるでしょう。
サワンの足に、ブリキの輪を嵌めてやろうとも思いました。
ブリキの輪には、月明りの空を高く楽しく飛ぶサワンへ、はなむけの言葉を刻んでやるのです。
しかし私が目を覚ますと、サワンの姿はどこにもありませんでした。
私は狼狽し、必死に家中を探しましたが、廊下の下にも屋根の上にも、どこにもいません。
沼地も確認しましたが、やはりサワンはいませんでした。
おそらくサワンは、雁の群れと共に旅立ったのでしょう。
私にできる事は、サワンの名を呼び縋る事だけでした。
屋根の上のサワン を読んだ読書感想
『山椒魚』で有名な、井伏鱒二の作品です。
自身の屈託した考えの元、保護した雁に執着にする孤独な人間の話です。
撃たれた動物を治療し、世話をするというのは、日本の御伽噺でよくある話の流れですが、男はどこか独りよがりで、ひたすら愛情への見返りを求めます。
ほの暗く、恐怖すら覚える主人公の言動ですが、それ以上に切なさを感じるのが、主人公の心に諦めが見えるからかもしれません。
作中、主人公はサワンを「友人」と呼ぶ事はありません。
更に、サワンが傍にいてくれるのは主人公を好いているからだ、とは一言も言わないのです。
ただ、自分の愛着をサワンが裏切るはずがない、と信じるのみです。
自身の屈託した思い・孤独感を癒すためだけに、サワンを縛り付け手元に置いている事。
その執着の異常性を、主人公は誰よりも理解しているように思えます。
そう思えば、サワンが必死で呼び縋る雁の群れを「サワンの友人」と表現せざるをえず、サワンを手放す事を決心しつつも、自分という存在を足枷として嵌めようとする行動そのものが、物悲しくなります。

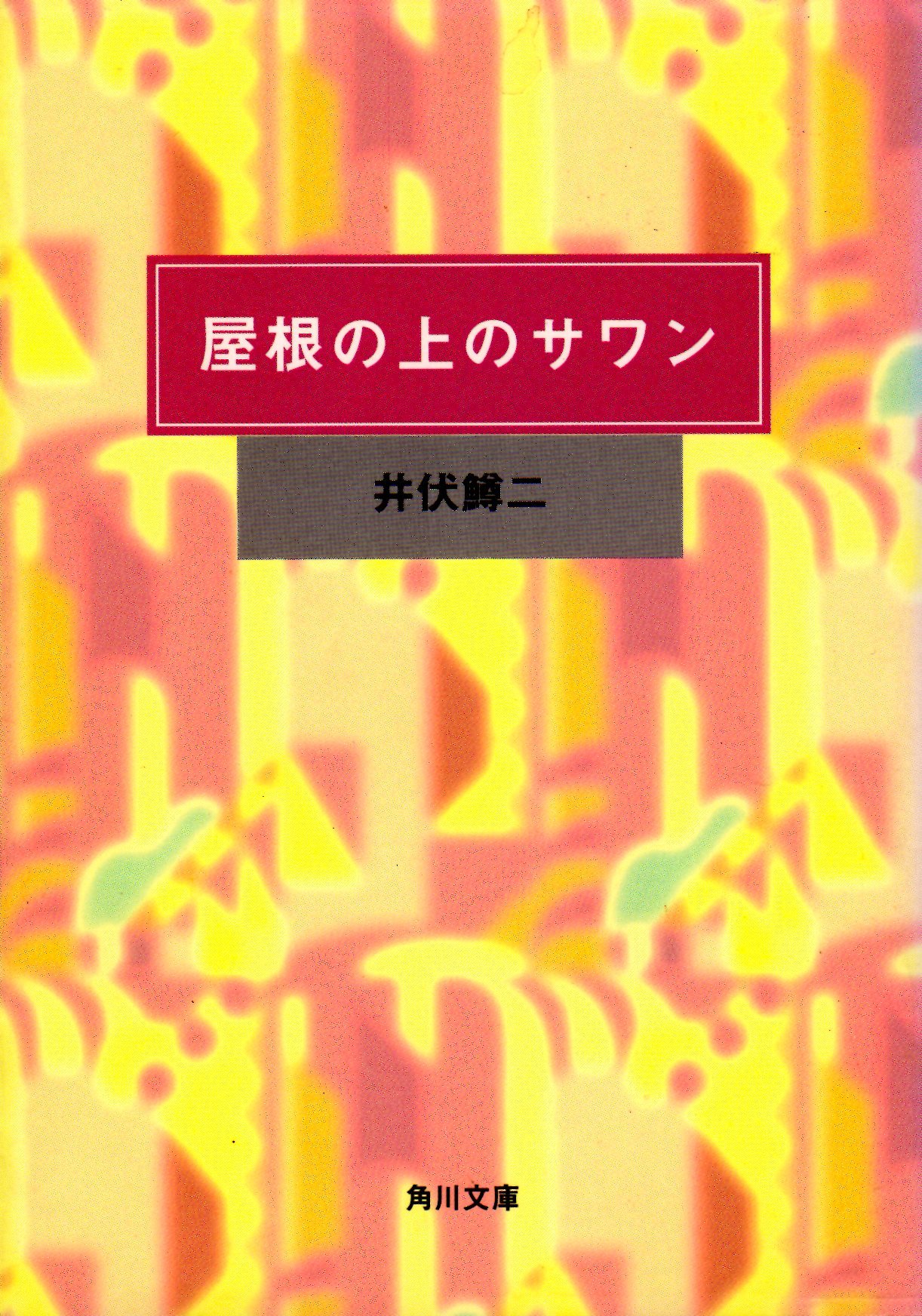
コメント