著者:谷崎潤一郎 1918年7月(雑誌掲載)に大日本圖書「雄辯」(雑誌掲載)から出版
人間が猿になった話の主要登場人物
留吉(とめきち)
芸者屋「春の家」の隠居のお爺さん。現在六十代。ただし、回想している物語のなかでは三十代。
お鶴(おつる)
留吉の妻。
丁次(ちょうじ)
若狭屋の抱えている芸者のひとり。売れっ子。
お染(おそめ)
若狭屋の抱えている芸者のひとり。売れっ子。丁次より一つか二つ若い。
内藤(ないとう)
お染をひいきにする客。やがてお染を落籍するつもり。
人間が猿になった話 の簡単なあらすじ
丁次とお染は、若狭屋という芸者屋の二枚看板でした。
ある日、猿廻しが若狭屋にやってきました。
と、突然、彼のつれていた猿がお染に襲いかかり、着物のすそを引っぱってはなしません。
若狭屋の主人が猿廻しを叱りつけてことを収めたものの、その日以来、お染に不気味な猿の影がちらつくようになります。
しだいに弱っていくお染が、ついに若狭屋の主人に告白したのは、猿から「自分と添い遂げてほしい」と迫られている、というものでした。
主人は占い師に相談したものの、打つ手はなく、結局お染は猿に連れられて失踪することになります。
人間が猿になった話 の起承転結
【起】人間が猿になった話 のあらすじ①
芸者屋の「春の家」の隠居、留吉爺さんは、話の上手なことで有名です。
今夜、お爺さんは「風変わりな話をしてあげよう」と言って、かかえている芸者たちを呼びました。
芸者たちは活動写真を見に行く予定を変更して、お爺さんのところへ集まりました。
お爺さんの話は、活動よりよほどおもしろいのです。
お爺さんは「三十年も前のことだがな」と話しはじめるのでした。
……当時、留吉は三十代でした。
妻のお鶴といっしょに、葭町に「若狭屋」という芸者屋を出したばかりのころです。
かかえている芸者は五、六人。
そのうちの丁次とお染のふたりが売れっ子でした。
丁次のほうがおそめより一つか二つ年上です。
性格的には丁次のほうがおもしろく、器量はお染のほうが上でした。
お染は呉服屋の娘で、父を早くに亡くし、継母に育てられたものの、暮らしに困って、十五、六のときに、若狭屋にやってきたのです。
すでに芸の心得もあり、読み書きもできましたが、どこかしら寂しげで陰気くさいところがありました。
芸者に出ると、仲買の野田さんとか、麻問屋の内藤さんといった旦那がひいきにしてくれて、留吉もひと安心したのでした。
さて、お染が十九歳の四月、若狭屋へ猿廻しがやってきました。
女たちが土間の次の間で食事しているところへ突然入ってきて、猿を踊らせはじめたのです。
女たちは驚き、悲鳴をあげて、となりの部屋に逃げていきます。
お染も逃げようとします。
ところが、猿がお染の着物のすそをしっかりとつかんで離さないのです。
猿廻しはおもしろがって見ているばかり。
そこへ駆けつけた留吉が叱りつけると、ようやく猿廻しは猿を引きもどして出ていったのでした。
【承】人間が猿になった話 のあらすじ②
女たちはいっとき騒いだものの、それきり別段気にとめていませんでした。
その夜、十二時すぎ。
お座敷から帰ってきたお染が、はばかりに入ってすぐに飛び出してきました。
真っ青な顔です。
お染が言うには、おちょうずをしようと思ったら、金隠しの下から毛むくじゃらの猿の手が出てきたととのこと。
すぐに留吉が調べましたが、おかしなものは見つかりませんでした。
「なにか勘違いしたんだろう」と留吉が言うのに対し、「いいえ、確かに猿がいたんです」とお染は強情をはります。
それから二、三日、お染は怯えていましたが、徐々に平静を取り戻していきます。
そうして十日ほどたったときです。
蒸し暑くて寝られない夜でした。
二時半ごろ、富吉が布団の中で講釈本を読んでいると、女たちが寝ている二階から、うなされているような声が聞こえてきます。
具合の悪い娘でもいるのかと、留吉は二階へ上がっていきました。
階段の途中で、うなり声の主はお染であるとわかりました。
二階の部屋のふすまを開けると、座敷には行灯がぼんやりと灯っています。
お染は行儀よく寝ていましたが、その掛け布団の上には、お染の胸を押さえつけるように、一匹の猿が座っているではありませんか。
よく見ると、お染は額にびっしりと汗をかき、頬は上気しています。
お染は強く胸をふくらませたりへこませたりしているようで、それにつれて猿の身体が上下します。
留吉はお染を起こさないようにしてコトをおさめようと考えます。
彼は縁側の雨戸を一枚開け、猿を手招きしました。
すると猿はおとなしく出ていったのでした。
朝になっても、留吉は猿のことをお染に話しませんでした。
お染を驚かさないように、という気づかいからです。
しかし、お染はだんだんと元気をなくし、やせ細っていくのでした。
【転】人間が猿になった話 のあらすじ③
そうこうするうち、四月の二十日ごろに、葭町の三業組合が合同で荒川へお花見に行くことになりました。
若狭屋の者たちも皆で出かけます。
船に乗って、皆で酒を呑み、三味線や踊りも始まります。
さて、船が吾妻橋をすぎて、竹屋の渡しへかかったころです。
どこに隠れていたのか、突然一匹の猿が現れ、お染の首に飛びついたのです。
お染は悲鳴をあげ、ほかの芸者たちは逃げ出します。
留吉はすぐさまお染のところへ行って、猿を引きはがそうとしました。
しかし、猿は執念深くお染の首にしがみついて離れません。
遅ればせながら、ふたりの船頭が手伝ってくれて、ようやく猿をひきはがすことができました。
川にたたきこんだ猿は、泳いで向こうの土手にあがり、去っていきました。
まもなく船は荒川土手に着き、皆は花見のために船をおりました。
お染は船の上で寝たきりです。
留吉がそれを看病します。
お染は留吉に告白しました。
自分は猿に見込まれてしまったのだ、と。
以前、猿廻しの騒動があった日、はばかりに猿の手が出たことがありました。
実はそれ以降も、お染の行く先々で、はばかりに猿の手が出てきたり、猿が仕事帰りのお染のあとをつけてきたりしたのです。
そうしてある晩のこと、寝ているお染の上に猿が乗っかって、「どうか私と添い遂げてください」と頼むのです。
さらには「もし承知してくれなければ、一生恨みます。
あなたと添い遂げようとする男があれば、その人をたたります」とまで言うではありませんか。
お染は助けを求めて怒鳴ったつもりですが、口がうまく動かず、うなり声しか出ませんでした。
そうやってお染が三十分も苦しんだ頃、猿は「よく考えておいてください」と言い残して、去っていったのでした。
【結】人間が猿になった話 のあらすじ④
それ以来、夜中の二時から三時ごろ、猿は必ずお染の寝床へ来るのだそうです。
そのたびに、お染はうなり声をあげます。
一度、留吉がそのうなり声を聞きつけ、二階にのぼってきて猿を追い払ってくれたのも、そんなときでした。
お染は、猿を追い払ってもらったあとも、あまりの不気味さに、寝たふりを続けたと言います。
また、留吉が追い払ってくれた晩以降も、猿は毎晩現れたのですが、お染のほうが助けを求めるのをあきらめたので、うなり声はそれきりやんだのでした。
また、先日、ひいき客の内藤さんと箱根の温泉に行った晩も、夜中の二時に猿は出てきて、お染の胸に乗っかったそうです。
そうして、「あなたがこの旦那と添い遂げるなら、この旦那の寿命を縮めます」と脅したのです。
お染からすべての事情を打ち明けられた留吉は、評判のよい占い師に相談しました。
占い師が言うには、「人間が獣に恋慕されることはままある。
その人がしっかりしていれば問題ないが、お染のように気弱だとはねのけられない。
もはや、いまとなってはどうすることもできない。
お染はやがて猿の言いなりになるでしょう」とのことです。
そうして実際、花見から半月ばかりあと、お染は姿を消してしまいました。
例の猿廻しを訪ねると、猿は逃げ出していました。
もともと野州で生け捕りにした猿なので、そちらへお染と逃げていったものと思われました。
内藤さんは野州のほうへ捜索に行きましたが、お染を見つけることはできませんでした。
ただ、それから五、六年後のことです。
お染の客だった人が塩原の温泉に行ったとき、山のほうで、ボロを着た女のようなものが猿と遊んでいるのを見た、ということです。
人間が猿になった話 を読んだ読書感想
オーソドックスな怪奇談で、非常に読みやすく、またおもしろかったです。
内容は、広い意味での異種婚姻譚というのでしょうか。
人間と獣との結婚を扱っています。
さらに範囲を絞るなら、異種婚姻譚のなかでも、獣が人間の女に恋をして無理やり結婚を迫る、というパターンと言えます。
これは、いくつか先行する作品があります。
有名なところではボーモン夫人の「美女と野獣」もそうですし、曲亭馬琴の「南総里見八犬伝」の始まりの部分もそうです。
そういった文芸作品で扱われているということは、それだけ人間にとってわかりやすくてかつ怖い、ということなのでしょう。
本作でも、谷崎潤一郎は、そのわかりやすいパターンをもとに、ぞくぞくするような怖い話を作り上げています。
はばかり(トイレ)に入ったら、毛むくじゃらの猿の手がにゅっと現れた、というシーンや、うなり声がするのでふすまを開けたら、行灯だけの冥い部屋のなか、猿が女の布団の上に鎮座していた、など、視覚的な怖さが随所にしかけられています。
そうしてラストは、猿と同化していった女のあわれさを描いていて、読んだこちらの胸のなかに、長く尾を引く余韻を残すのでした。

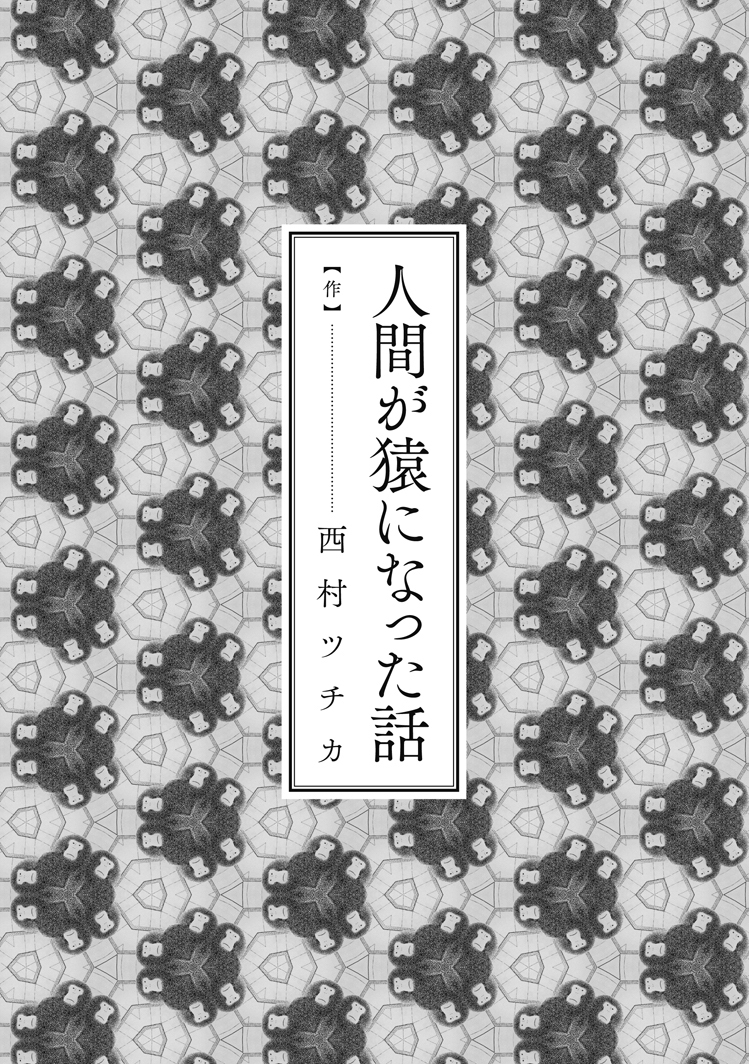
コメント